- 新55年体制 -
2019/12/20
立憲民主党の枝野代表が、共同会派を構成する立憲民主党、国民民主党、社民党、社会保障を立て直す国民会議、無所属フォーラムに、政党合流を呼びかけたのは12/6のことでした。以降、国民民主党や社民党は党内調整を進め、政策協議や地方組織をどうするかなどの問題はあるものの、「大きな塊」に向かって動き出しました。
この陰には、昨年から岡田克也衆議院議員らと行動を共にし、今年初めには立憲民主党会派に加わった、元自民党の大物、中村喜四郎衆議院議員の動きがあります。中村衆議院議員は、共同会派の立憲、国民、社民をとりもつだけでなく、共産党との共闘にも力を入れ、高知知事選挙での共産党出身候補の応援で野党共闘を実現させたことも記憶に新しいところです。また、自民党時代の人脈で石破茂衆議院議員や山崎拓元衆議院議員などとの会談も重ねており、なにやら自民党も巻き込んだ政局の仕掛けを期待させます。
中村衆議院議員の動きには「消費税5%減税」を掲げるれいわ新選組との距離感が見えませんが、れいわ新選組との連携は同じ故田中角栄元総理の愛弟子、小沢一郎衆議院議員の担当でしょうか。また、前回落選した野党議員を束ねた一丸の会の馬淵澄夫衆議院議員も、消費税減税を軸に共産党やれいわ新選組を含めた幅広い野党結集に向けて動いています。
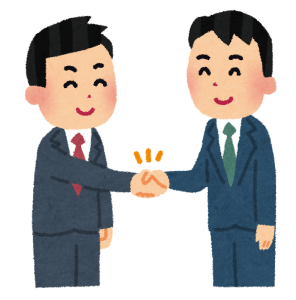
このような野党の合従連合の動きに取り残されているように見えるのが、日本維新の会です。
今国会での菅原一秀、河井克行2閣僚の辞任や「桜を見る会」疑惑追及で共同会派や共産党の活動が注目される中、維新の会は国会終盤で内閣不信任案の提出・解散を主張したり、臨時国会会期延長に賛成するなど、いつもとは異なる動きを見せたものの、国会での存在感を示すことはできませんでした。国会閉幕後も、共同会派の政党合流など、次期衆議院選挙をにらんで各勢力が動くなか、維新の会の目立った動きは報じられていません。
維新の会は、現政権の経済政策や外交などに関して反対というわけではありません。また、大阪を拠点とする維新にとって、大阪万博の開催、IR誘致などには、現政権のバックアップが必要不可欠です。ゆ党と揶揄されながら、他の野党と一線を画した第三勢力を標榜してきたのですが、野党結集の動きに対し維新の会はどのようなスタンスで臨むのでしょうか。
さて、「維新」といえば橋下徹さんですが、最近ではプレジデントオンラインの12/10配信の記事を始めとして、安倍政権の「桜を見る会」疑惑に対する対応を厳しく批判しています。特に、公文書の管理(記録、保存、公開)をないがしろにする政権の体質に警鐘を鳴らしています。
日本維新の会の足立康史衆議院議員は、このプレジデントオンラインの記事に以下のようにリツイートしています(12/11)。
「新55年体制を壊す」というのは足立衆議院議員の持論です。1955年に確立された自民党と社会党の二大政党体制(=55年体制)と同じ状況が現在も現出しており、これが安倍政権の公文書軽視の一因だというのです。つまり、自民党と社会党が与党と野党第一党を分担し、表面上は保守vs革新の対立構図を演じながら水面下で手を握って政治を行ってきた55年体制と同じく、現在の「自民党+公明党」vs「維新以外の野党」も対立を装いながらも水面下ではなれ合っている体制(=新55年体制)ととらえているのです。
自民党vs社会党の55年体制が崩れてから久しく、政権交代は経たものの、安定した二大政党制はいまだ確立されていません。これまでの、日本維新の党、みんなの党、たちあがれ日本など保守政党の乱立や集散、かたや、民主党、日本未来の党、民進党、希望の党などの迷走を経て、今回の野党共闘の動きがようやく二大政党を形作る気配となりました。このまま野党サイドが統一され、選挙を経てある程度拡大することになれば、新55年体制はより強固なものとなり、水面下での与党との関係もより緊密になる、との危機感が足立衆議院議員にはあるのでしょう。
今回の野党共闘が、緊張感を持った二大政党に育つのか、対立を演じるなれ合いの二大政党に堕するのか、はたまた結集に失敗してしまうのかは神のみぞ知るですが、それでは、野党統一の構想から外れている維新の会は、新55年体制をぶっ壊してどのような新しい勢力図を目指すのでしょうか。また、「あと一年」とは?
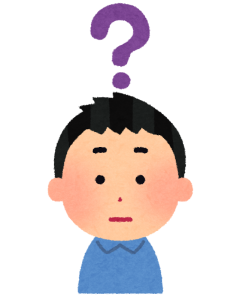
「桜を見る会」疑惑で安倍政権はかなりのダメージを受け、共同通信の12月世論調査では内閣支持率は前月比6ポイント減の42.7%で不支持が逆転しました。このまま疑惑が終息しないのであれば、自民党としてもトップの交代を図る動きがでてくるでしょう。安倍総理個人や安倍政権中枢による「桜見る会」の私物化という疑惑と政府の対応への不信が、安倍総理周辺だけではなく自民党全体への不信として波及・拡大していくことは明らかです。その傾向が、自民党の政党支持率の低下に表れつつあります。
そのためか、マスコミ世論調査の次期総理候補では石破茂衆議院議員への期待が高まってきています。「桜を見る会」疑惑が安倍総理に極めて近いところに存在し、かつ長期政権の腐敗が指摘される中、政権中枢から遠い石破衆議院議員は、一連の疑惑から最も遠い存在として、ポスト安倍には適任ということになります。
かたや安倍政権を支え続け、ポスト安倍の一人と目されるまでになった菅官房長官はどうでしょう。自民党内でトップ交代の流れになった場合、菅官房長官が無派閥議員や安倍チルドレンを中心に支持を取り付けて総裁選に出馬することは可能でしょうが、「桜を見る会」批判の矛先が菅官房長官にも向いてきている現状をみると、自民党内の派閥力学が選挙での敗北を恐れ、安倍政権の中枢であった菅官房長官を新総裁とすることを拒むのではないでしょうか。菅官房長官にとっては、ポスト安倍の新政権と統一野党との間で新55年体制を築かれてしまっては、これまで政権の中枢で蓄積してきた権力や野党とのパイプを失ってしまうことになりかねません。ここは、現政権を支え、とりわけ自民党内で延命を図るしかありませんが、野党の攻勢に対しどこまで時間が稼げるでしょうか。
仮に、新55年体制というものが存在し存続し続けるとしても、与党サイドもまた変化を求められています。

以上のことから推測すると、以下のような構図が浮かび上がります。
自民党から共産党までを相手に会談(密談?)を重ねる中村衆議院議員の動きや、かねてより「新党結成は年内が望ましい」と繰り返し発言している合流推進派の国民民主党小沢一郎衆議院議員の目指す勢力図は、
(石破自民党+公明党)vs(統一野党+共産党)
自民党内が穏便に石破衆議院議員へのトップ交代を進めてしまえば、総選挙を経ることなく新55年体制が敷かれ、2021年の任期満了近くでの総選挙を実施すれば、政権交代はともかくバランスのいい二大政党の構築が可能になります。
一方、他の野党と合従連衡しない維新の会の勢力拡大は、選挙しかありません。東京オリンピック後の解散総選挙を見据えて「あと一年、万全の準備をし」相当数の立候補者をそろえることになるのでしょう。しかし、統一野党を抑えて野党第一党の座を得ることは、簡単ではありません。
維新の会は政策的には他の野党よりも自民党に近く、維新の会の幹部には「我々は菅派だ」と自認する方もいます。統一野党勢力と一線を画してきた維新の会は、菅官房長官の勢力とより緊密に連携するチャンスでもあります。創始者である橋下徹さんの安倍政権への批判も公文書管理に関するものであり、安倍政権の政策について批判しているわけではありません。新55年体制を打ち壊す、新しい対抗勢力を共に目指すことは可能なのではないでしょうか。
橋下さんと足立衆議院議員の発言から見えてくるのは、一年後の総選挙を経た、
(石破自民党+統一野党)=新55年体制 vs (菅自民党+維新の会+公明党)
まずは表面上の「与党vs野党」とは別に、水面下で緊張感のある対立構造をつくり存在感を示す、これが維新の会が目指す新しい勢力図ではないでしょうか?
この構図は、必ずしも自民党の分裂を意味するわけではありません。しかし、巨大政党である自民党の安倍一強体制が崩れれば、党内に存在する様々な対立が顕在化し、党内政局化しやすい状態となることは想像できます。現在でも、維新の会の地元「大阪都構想」に対する賛否や東京都知事選挙の候補者選定に見られるように、中央と地方の対立は既に存在しています。また、次々回衆議院選挙では2020年国勢調査に基づく選挙区割の大規模な改定が予定されており、これに伴う公認争いが派閥の勢力争いを助長することにもなるでしょう。このときこそ、政界再編を仕掛ける維新の会が新55年体制をぶっ壊し、野党第一党、あるいは政権与党入りをかけた勝負に出るのではないでしょうか。

