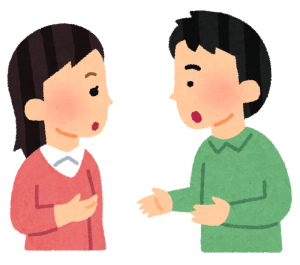
- あのときのこと -
2020/1/18
立憲民主党枝野代表が、野党共同会派を構成する立憲民主党、国民民主党、社民党、社会保障を立て直す国民会議、無所属フォーラムの政党合流を呼びかけたのは2019/12/6 のことでした。以降、立憲民主党福山幹事長と国民民主党平野幹事長は会談を重ね(12/19-27)、2020年の年初に党首会談にて立憲民主党と国民民主党の政党合流の結論を得ることとなりました。
ところが、2020年が明け、枝野代表と玉木代表は2回の非公式党首会談(1/7,1/9)を経て、公式の党首会談(1/10)に臨みましたが、政党合流の合意には至りませんでした。立憲民主党が国民民主党の吸収合併を主張するのに対し、国民民主党は対等合併を求め、折り合わなかったようで、これで通常国会が始まる1/20までの合流は日程的に不可能となりました。
玉木代表は、なおも協議の継続を求めていますが、枝野代表は1/20で協議を打ち切る方針のようです。
この背景には、人事面などでの主導権争いもあるようですが、政策的には立憲民主党の原発ゼロ基本法案を国民民主党を支援する連合(電力労連)が受け入れられないのが主因とされています。
しかし、国民民主党玉木代表は、「原発ゼロ基本法案の撤回」の他に、党名や綱領にもこだわったと報道されています。
『綱領に「改革中道」という文言を明記』
これは何を意味するのでしょうか。
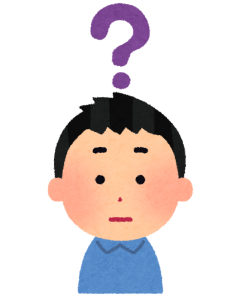
2017年に遡ると、前原誠司代表(当時)の民進党は衆議院議員選挙に臨み、自党からは候補者を擁立せず、立候補者は小池百合子代表(当時)の希望の党の公認を得て選挙を戦うこと決めました。しかし、小池代表は、民進党の候補者全員を受け入れることはせず、「安全保障、憲法観など主要政策の異なる者は排除する」と宣言しました。いわゆる『排除の論理』です。これに反発した民進党のリベラル系議員が設立したのが枝野幸男氏を代表とする立憲民主党です。
選挙後、大敗した希望の党は解散し、希望の党のコアメンバーではなかった民進党出身者の多くは、民進党の参議院議員とともに国民民主党を結成しました。
立憲民主党と国民民主党は、 両党間での移籍や無所属のまま選挙を戦った人たちの合流もありましたが、設立の経緯から国民民主党は保守寄り、立憲民主党はリベラルと色分けされています。
この経緯を踏まえれば、国民民主党が「改革中道」を掲げるのは当然といえば当然ですが、立憲民主党にとっては今回の合流新党の綱領に「改革中道」を書き込むことは、党のリベラル色を薄めててしまうことになります。これは立憲民主党のリベラル系の人たちには抵抗があるでしょう。また、社民党など左派系の人たちが新党に合流するハードルを上げてしまうことにもなりかねません。
左/右というイデオロギーは過去のもの、立憲民主党枝野代表さえお正月には伊勢神宮、出雲大社に参詣するご時世とはいうものの、「中道」という言葉自体が「左」と「右」の存在を意識させます。立憲民主党は、左から右へウイングを延ばそうとしていますが、「リベラル」という看板から想起される「改革派」「市民派」の支持層も失いたくはないでしょう。
それにもかかわらず、玉木代表はなぜ「改革中道」にこだわるのでしょうか。

衆議院を俯瞰すると、自民会派の議員は2020/1/16現在で284名です。衆議院定数は465ですが小選挙区は289。自民党の現職議員全員が小選挙区で立候補するとなると、選挙協力で公明党に譲る選挙区もあり、引退などの欠員がなければ新人が立候補できる選挙区はない、という状況です。しかも、引退議員が身内に世襲させたり、野党を離党した議員や無所属議員が自民党に続々入党するなど、選挙区の奪い合いは激化し、国政選挙で落選した古株の元職が、地方の首長選挙や地方議員選挙に出馬するなど逆流現象も起こっています。
一方、地方の市議会議員などは保守系無所属の方が大半ですが、自民党はこういう方々のすべてを組織として取り込んでいるわけではありません。自民党議員は個人商店といわれるゆえんでもあります。このような方々が上を目指して政治家としての階段を上っていくのに、自民党の階段の先は飽和状態の狭き門で、そこからはみ出した方々は別の道を探さなければなりません。以前は、旧みんなの党や維新の会などの保守政党がその受け皿となっていましたが、党勢を拡大することができずに「保守=自民党」の陰に埋没し、その機能を果たせなくなっています。一強巨大与党の弊害の一つとして、国政を目指す若き保守系地方議員の行き場がなくなっています。
このような方々を支持者ごと取り込んで党勢拡大を図ることは、地方組織の弱い立憲民主党にとって最優先の戦略となるはずです。しかし、リベラル色の強い「立憲民主」の看板では、「市民派」「改革派」の地方議員を取り込むことはできても、「中道」より右の人たちを自陣営に引き込むことはなかなか難しいと思われます。
それでは、このような方々が支持率上昇の兆しもない国民民主党に身を委ねるかといえば、こちらも望み薄でしょう。
玉木代表が政党合流に際して党名や綱領にこだわるのは、この点ではないでしょうか。

立憲民主党のコアなリベラル支持者を囲い込みつつ、新たな「中道」の看板で保守系の地方議員やその支持者たちを取り込んでいく。リベラル一辺倒ではなく中道保守も取り込まなければ、大きな塊にはなりません。「右:自民党」「中道:(立憲+国民)新党」「左:共産党」の三極構造を構築する。そして、「右:自民党」とりわけ安倍政権を倒すため、今は「中道」+「左」で共闘する。しかし、自民党内で安倍勢力が駆逐され、「右」が一強でなくなった暁には、「右」+「中道」で「左」と訣別する。
「右」と「中道」はその大きさによって、新55年体制もしくは二大政党として与党と野党の役割を演じることになるのでしょう。
もはや、「右」や「左」にイデオロギー的な意味はありませんが、「中道」と「左」の間には深い溝があります。
共産党も含めた野党共闘を推進する中村喜四郎衆議院議員は「野党共闘は、消費税の上げ下げのような小さい問題ではなく、安保政策こそ政権を担うカナメ」と述べていますが、この発言の裏には、「政権を取ったとしても共産党は閣外」という考えが透けて見えます。この安保政策こそ「中道」と「左」を隔てる深い溝、思えば希望の党が踏ませた「踏み絵」に他なりません。「踏み絵」を踏まなかった立憲民主党の面々を「中道」の側へひっそりと転向させる、それが玉木代表のもくろむ新党構想ではないでしょうか。民主党ではなく「排除する前の」希望の党への回帰、あの時「踏み絵」を出さなければ構築できた政権交代の道筋への回帰です。
あの時、「踏み絵」とは別の理由で希望の党から排除された人たち、無所属で戦うことを余儀なくされた民進党の重鎮だった人たちも、この回帰を望んでいるのではないでしょうか。一方で、立憲民主党のリベラル代表格の赤松広隆衆議院議員はこれを察知したのか、玉木代表の提案を激しく拒否しています。
小池百合子代表(当時)がなしえなかった希望の党政権への再挑戦。枝野代表はリベラルへのこだわりを捨ててこの神輿に乗ることはできなかったのでしょうか。決断を迫られていたのは、枝野代表の方だと思えてなりません。

